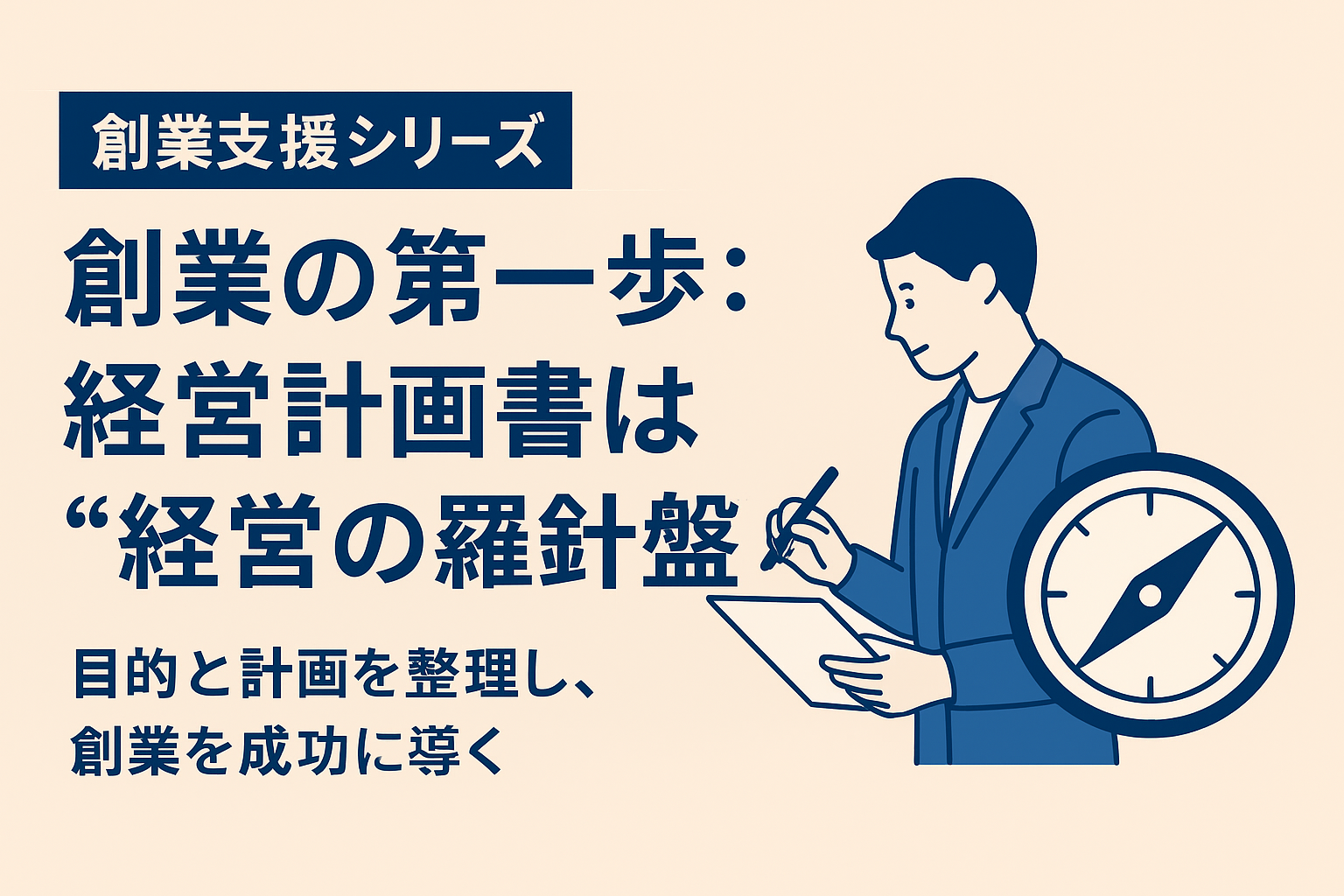創業の第一歩は、書類ではなく「思考の整理」から始まります。
経営計画書を作るというと、「役所に提出するための面倒な書類」と思う方が少なくありません。
しかし、経営計画書とは、単なる申請書ではなく「経営者自身の考えを言葉にし、未来を描くためのツール」です。
創業の流れと必要な準備
創業を進める際には、大きく以下のステップがあります。
- ① アイデアを整理する(何を・誰に・どう売るのか)
- ② 市場や競合を調べる(ニーズや価格帯を把握)
- ③ 事業計画書を作成する(数字とストーリーを整理)
- ④ 資金計画・資金調達を検討する
- ⑤ 実際に事業をスタートする(販路開拓・顧客対応)
この流れの中で、経営計画書は「①〜④をつなぐハブ」として機能します。
つまり、創業を思いつきで進めるのではなく、計画という“地図”を持って出発することが重要です。
創業の目的を明確にする(なぜ創業するのか)
創業を考えるとき、最初に立ち返るべきは「なぜ自分は創業したいのか」という問いです。
単に「独立したい」「儲けたい」という動機だけでは、厳しい局面を乗り越えられません。
経営計画書をつくる過程で、自分の価値観や社会への貢献意識を整理していくと、事業の方向性が自然に定まります。
この「原点の確認」が、後のブランディングや顧客への説得力にもつながります。
自分の強み・価値を見極める(知的資産経営の視点)
創業時は「自分に何ができるのか」を見極めることが重要です。
ここで有効なのが、知的資産経営(Intellectual Asset-based Management)の考え方です。
知的資産とは、ノウハウ・人脈・ブランド・信頼・組織文化など、財務諸表には現れない「見えない資産」のこと。
これらを言語化し、どう活かすかを考えることで、他者との差別化ができます。
たとえば、前職で培った専門スキル、地元顧客との信頼関係、迅速な対応力なども立派な知的資産です。
これらを棚卸しすることで、自分の強みを軸にした戦略が描けます。
成功する創業者に共通する考え方(Effectuation理論の紹介)
ビジネススクールで注目されている理論のひとつに、Effectuation(エフェクチュエーション)があります。
これは、アメリカのサラス・サラスバシー教授が提唱した、成功した起業家の意思決定パターンを分析した理論です。
従来の「目標を決めてから手段を探す(Causation)」とは異なり、
Effectuationでは「今ある手段(自分・仲間・知識・手持ち資源)」から始めて、できることを広げていくという発想を取ります。
創業初期は、理想を描くよりも「いまあるリソースでできること」を積み重ねるほうが成功しやすい。
そしてその積み重ねの中で、協力者が増え、方向性が洗練されていくのです。
経営計画書は「自分の考えを形にするツール」
経営計画書を作る最大のメリットは、「頭の中のもやもやが整理される」こと。
文章にしてみると、自分でも曖昧だった部分が見えてきます。
数字を書き出すことで、現実的に何ができるかを考えられ、計画の実行力が高まります。
創業の成否を分けるのは、才能ではなく「準備力」と「整理力」です。
まとめ:創業の第一歩は、紙を書くことから始まる
創業のスタートは、頭の中のアイデアを紙に書き出すことから始まります。
経営計画書づくりは面倒に見えて、実は「自分の未来をデザインする作業」なのです。
当社では、創業希望者の考えを整理しながら、計画書作成のプロセスを伴走支援しています。
一度仕組みを理解すれば、次からは自分で考え・書けるようになります。
創業の準備、どこから始めたらいいかわからない方は、こちらのフォームからお気軽にご相談ください。